
時代とともに変化を見せるアニメ・ソング。近年、よく見られるようになったのは、声優自身が歌うだけでなく、ダンスや楽器演奏まで行うパフォーマンスだ。現在のアニメ・ソングを語る上で欠かせない、この“声優のアイドル化”と言える現象について、声優マネジメントを行っているStyle Cubeのたかみゆきひさ氏に解説いただこう。
Text by たかみゆきひさ(Style Cube)
アイドルとアイドル声優の“大きな”違い
歌ったりライブをしたりとアイドル的な活動が多く、音楽とは切っても切れない昨今の声優についてまず認識しておくべきことがあります。というのは、声優業界って実は知っているようで知らないことが意外と多いのです。と、ここで質問。そんな“声優”とAKB48のようないわゆる“アイドル”との違いって分かりますか? どちらも歌ったり踊ったり写真集を出したりと、活動的な違いはあいまいで、声優は主にアニメなどのアフレコをしているくらいしか思い付かないでしょう。細かいことを言うと“アイドル”とは業態であって職業ではありません。アイドル声優というのはアイドルという業態の声優で、AKB48などはアイドルという業態の歌手やタレントであり、ここで言う違いはそういうことではないのです。では一体何か……。
“アイドル”と“声優”の大きな違い、それは“自身がコンテンツか否か”。コンテンツに対する基本姿勢が全く違うのです。声優はアニメなどのコンテンツに依存し、それら無くして声優は成り立たない。一方、AKB48などのアイドルは自身がコンテンツで、それを前提として活動しています。キャラクターという視点から見るとアイドルは自分自身がキャラクターであり、声優は“他者が創造したキャラクターを構成する一部”。これによってどういうことが起きるのか、一つの例を紹介しましょう。
アニメには登場人物が歌うキャラクター・ソング(キャラソン)というものがあって、キャラとして歌うのは声優にとっては演じることの延長として容易にイメージできます。しかし一般のアーティストのように“自分らしさを出して、歌いたいように歌って”と言われるとフリーズして歌えず、苦労する声優が意外といるのです。また、声優のアイドル・ユニットはもともとキャラが成立している“作品がらみ(コンテンツ依存型)”のものが多いです。『ラブライブ!』『アイドルマスター』『BanG Dream!』など、作中にアイドルが存在し、その声優が同名ユニットとして活動することがほとんど。作品ベースでは無い(=自分自身をコンテンツとする)声優ユニットは意外と少ないのです。
アニソン歌手と声優
アニソンはアニソン歌手が歌うべきだ、という意見があります。その気持ちはとても分かります。しかし、声優が歌うアニソンもとても重要なのです。アニソン歌手が歌うアニソンは、“歌を通して作品テーマを伝えることに長けた人によるもの”で、声優が歌うアニソンのポイントは“出演者が歌うという説得力”。思い起こせば、『タイムボカン』のエンディングのように出演声優が歌うアニソンは昔からたくさんあります。あのドロンボー一味が歌うエンディングの説得力と言ったらもうすごいなんてものじゃないし、山本正之が歌うオープニングの説得力も半端ではありません。両者はどちらも大きな意味を持って存在しているのです。
昨今の声優はキャラクターとして歌うときと、アーティストとして歌うときがあります。この両者は前述のように違うので、声優は“さまざまな局面に対応した表現力”を求められることに。そう考えると結構大変ですね。しかしこれは時代が望んでいるものであり、売れている声優というのは、そういった要望に応えられて結果を出している人たちなのだと思います。とは言え、キャラで歌うというのは実は難易度が高いです。例えば、イケメン低音ボイス・キャラの場合、歌うとどうしても音程が合わせづらい、レコーディングではなんとかなってもライブでは歌えないなどの弊害が出てくるので、楽曲制作側も声優側もそれなりの苦労が伴うのです。
声優のアイドル化と未来
日本のアイドルは海外のそれとは大きく違い、歌のうまさなどが評価基準とは限らない固有の文化です。これは“わびさび”が成立する日本文化の特徴がベースになっています。僕はよく“アイドルは盆栽”と例えるのですが、日本では盆栽のような曲がった木に価値を求め、西洋は真っ直ぐで奇麗な形状に剪定された木に価値を求めます。そしてアニメのような作品(コンテンツ)につながる大事なこと……日本のアイドルは実は“物語”なのです。売れていく過程、挫折、成功、ユニット卒業や脱退といったことまでもがそのアイドルの物語となり、ファンはそこに共感する。これがアイドルそのものがコンテンツたるゆえん。なので、アイドル・ソングとは言わばそのアイドルという物語における“キャラソン”なのです。
僕は1980年代から芸能界でずっとアイドルにかかわってきたので、アイドル声優に対して違和感がありました。前述のように、声優は自身がコンテンツではないため物語性が薄かったのです。もちろんこれには理由があります。声優業界は完成されたものを見せようとし、成長過程を見せることがほとんどありません。見せる必要も無かったわけですね。そこで僕らが考えるアイドルを声優業界に投じたいと考え、デビューさせたのが小倉唯と石原夏織という2人の声優によるユニット=ゆいかおり。ゆいかおりは、2008年の結成以前からその成長過程を敢えて大衆に見てもらえるようにしました。若くてかわいい10代の声優が歌って踊るユニットですが、最初はなかなか受け入れてもらえませんでした。10人くらいしかお客さんがいなかったゆいかおりは、やがて国立代々木競技場第一体育館でコンサートができるほどの人気となり、乃木坂46などの人気アイドルの中にゆいかおりファンが生まれるようにもなったのです。ゆいかおりは多くの“物語”を生みました。

また、ゆいかおりはレーベルの意向によりタイアップに頼らないユニットだったので、これとは別にタイアップ曲を歌うアニソン・ユニットとして、ゆいかおりの2人を含む4人組=StylipSをデビューさせました。かっこいい/かわいいダンスとともに、楽曲制作においてもさまざまな挑戦が行われました。StylipSのデビュー以降、楽曲のオーダーが大きく変わったと言われています。特に顕著だったのは、イントロや間奏などの歌っていない部分。それ以前はなるべく短くするなど、声優がステージで歌う際に“困らないように”工夫していたのですが、逆にイントロや間奏はダンスの“見せ場”になるため、そういったことを意識した楽曲になりました。こうしてゆいかおりとStylipSは今のアイドル声優のフォーマットとなり、自身がコンテンツになるスタイルも確立。これらのユニットに憧れて声優を目指す若い子も増えました。


『アイドルマスター』のような従来からあるコンテンツ連動型アイドル声優も、『ラブライブ!』の成功によりさらに隆盛を極め、以降アイドル関連作品や出演声優が主題歌を歌う作品が増加。それにより、数多くのアイドル声優も誕生しました。また、ライブ・イベントもたくさん行われるようになり、声優業界はさまざまなことに対応すべく、声優本人たちだけでなくマネジメント体制もかなり変わりました。今後は飽和による収縮やコンテンツとして飽きられないようにしていくことが課題であり、YouTubeなどで声優自身がコンテンツとなって発表できる場も増えたため、さらなる多様化への対応が望まれます。声優たちにとって変革期はまだまだ続くでしょう。
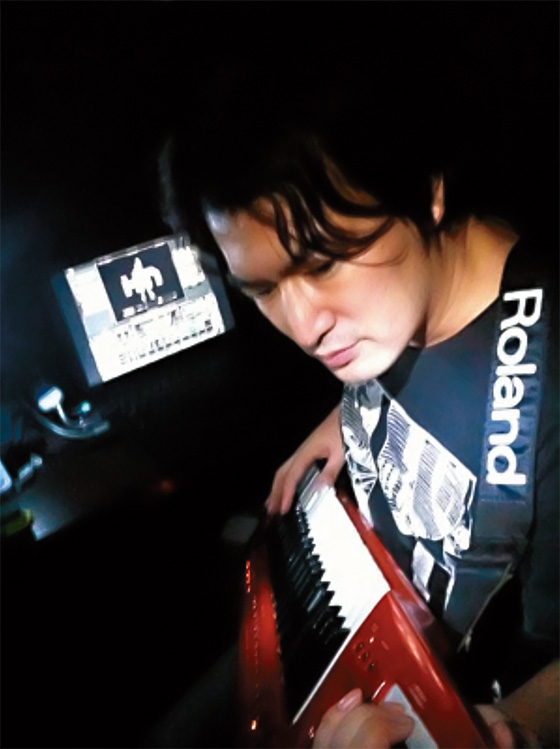
たかみゆきひさ(Style Cube)
【Profile】1990年代初頭、“アイドル冬の時代”脱却を目標に新しいアイドル・ビジネス・フォーマットを構築(ライブ・アイドルの基盤)。芸能界での経験を生かし、現在は声優のマネジメントのほか、音響制作やモーション・キャプチャー事業など多岐にわたり展開している。スタイルキューブ代表取締役。
関連記事



