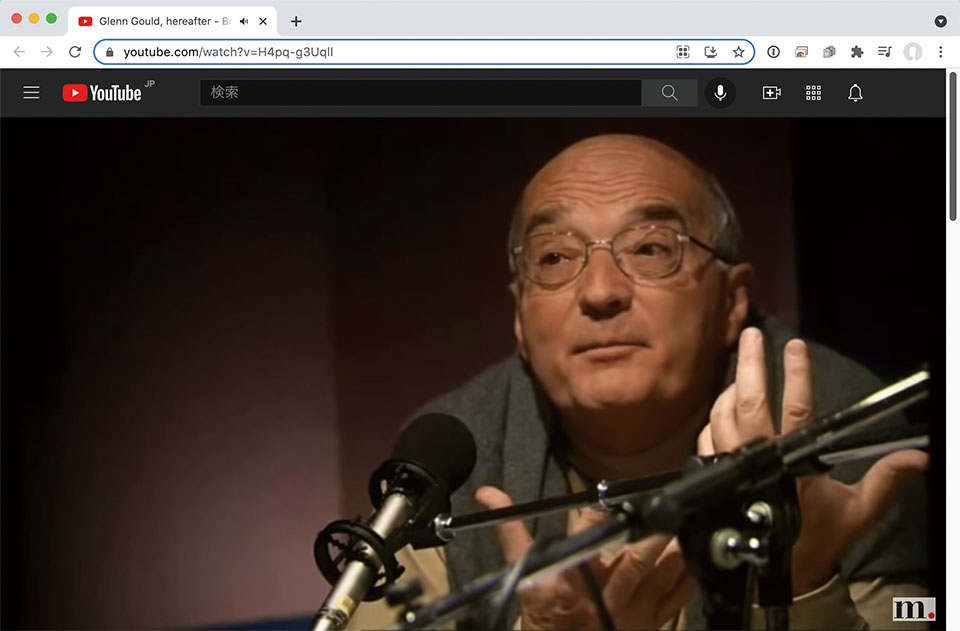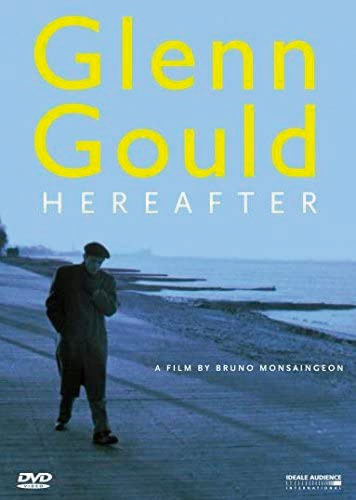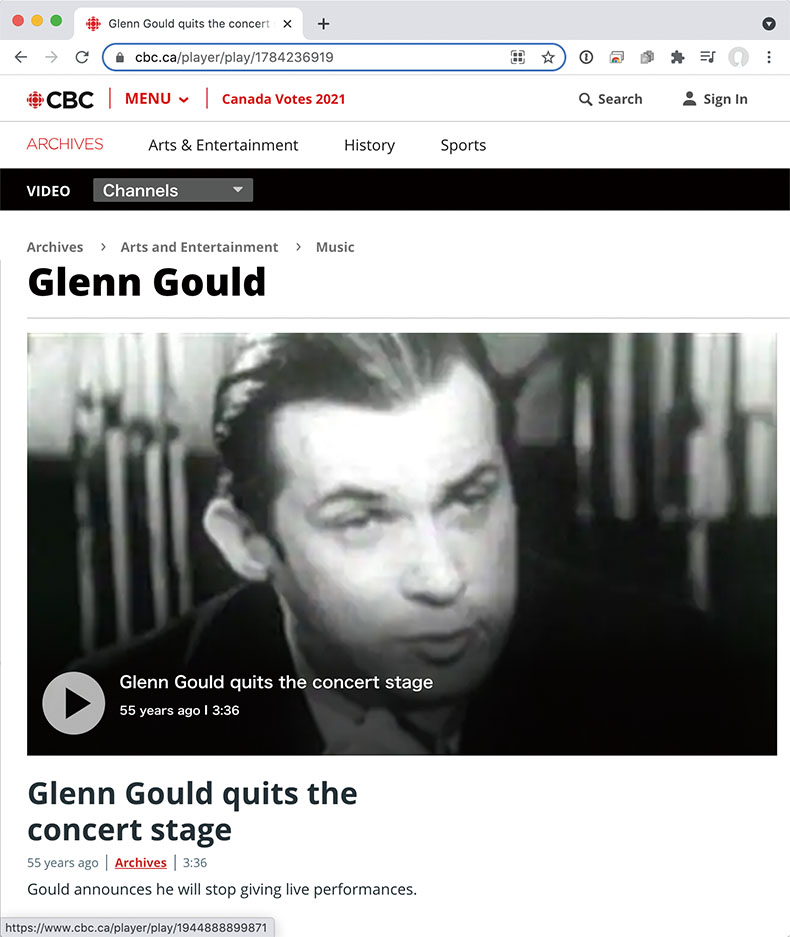グールドの演奏に内在していたテープ編集に向かう必然性
1955年の『ゴールドベルク変奏曲』のレコーディング・セッションの模様は、フランスの映像作家、ブリュノ・モンサンジョンが2006年に公開したドキュメンタリー映画『Glenn Gould, hereafter』の中にも垣間見ることができる。帽子とコート、マフラー、手袋でしっかり防寒したグレン・グールドが、ニューヨークの街角でタクシーを拾い、東30丁目のコロムビア・スタジオに向かうシーンは、1950年代にカナダの放送局が制作した再現映像のようだが、エンジニアのハワード・H・スコットが待ち受けるスタジオ内部の光景はリアルだ。コントロール・ルームではなく、レコーディング・ルームに置かれた巨大なモニター・スピーカーで、グールドがプレイバックを聴くシーンもある。
https://youtu.be/H4pq-g3UqlI
Nruno Monsaingeon
(EuroArts/Naxos/2006年)
グールド自身のナレーションや演奏映像を交えながら、彼の生涯と演奏を振り返るドキュメンタリー。現在はAmazon Prime Videoなど映像配信サービスでも鑑賞可能
1956年1月発表の『ゴールドベルク変奏曲』のオリジナルLPはモノラルで、後にステレオ盤も制作されたが、それは擬似ステレオだった。このことから、録音自体が完全なモノラルだったと考えられる。STEINWAY CD19の周囲に4本のNEUMANN M49をセットアップしたマルチ・マイキングで、AMPEXのモノラル・レコーダーに録音したのだろう。この『ゴールドベルク変奏曲』の時点では、グールドはまだテイクの編集を施すこともしていない。ごく普通のソロ・ピアノ演奏のレコーディングだったと思われる。
『ゴールドベルク変奏曲』は32曲あり、冒頭と最後のアリアに挟み込まれて、短い変奏曲が連なっていく。グールドの演奏はテンポが速く、その意味ではテクニカルだが、しかし、技巧を顕示するようなところは感じさせない。極めてクールに、音楽の構造を浮かび上がらせるような演奏だ。
1955年6月のセッションで収録されたすべてのテープを音源化したボックス・セット『グレン・グールド/ゴールドベルク変奏曲コンプリート・レコーディング・セッションズ1955』を聴いていくと、グールドの演奏はアウトテイクでもテンポがほぼそろっているのにも気付く。その時々の気持ちに任せて弾くのではなく、ある意味、テクノ・ミュージックのような冷徹さや端正さを香らせている。そういう構造性を持っていたからこそ、グールドのピアノ・ミュージックは、テープ編集へと向かっていたのではないかとも思われる。

レコーディングに専念するグールドが受けたヨゼフ・ホフマンからの啓示
『グレン・グールド/ゴールドベルク変奏曲コンプリート・レコーディング・セッションズ1955』は、グールドとスコットのトークバックでのやりとりが聴ける点でも面白い。それがセッションの中で変化していったことも分かる。
普通ならば、演奏が始まる前に“テイク1”“テイク2”と声をかけるのは、コントロール・ルームに居るプロデューサーやエンジニアの仕事だ。ところが、セッションの途中、5枚組CDのDISC2から3にかけては、グールド自身がテイクを数えて、演奏を始めることが増えている。弾き始めてすぐにやめ、最初から弾き直したり、練習を始めたり。グールドのペースで録音を進められるようになったのが分かる。ところが、セッションの終盤となるDISC4や5ではまたスコットがテイクを数えるようになる。テイクやテープの管理のために、通常のレコーディングのルールに戻したのかもしれない。
レコーディング・エンジニアにとって、グレン・グールドは必ずしも仕事のしやすい相手ではなかったようだ。グールドの演奏には2つのノイズがつきまとった。一つはグールド自身の声だ。グールドはうめくような歌声を発しながら、ピアノを弾いた。エンジニアはなるべくそれを拾わないようにマイキングを考える必要があった。
もう一つはグールドが欠かさず持ち歩く椅子だった。グールドは鍵盤に顔を近付けた、極端に低い位置で、猫背になってピアノを弾くのは、彼が10歳のころに父親が製作した高さの低い椅子のせいだった。その折りたたみ式の椅子はギシギシというノイズも発した。年を経るにつれて、ノイズは大きくなったが、グールドは決して、その椅子を手放さなかった。
グールドはピアニストとしては自分のやり方を曲げることはなく、それでいながら、プロデューサーやエンジニアの領域にも踏み込んでくる演奏家だった。『ゴールドベルク変奏曲』のセッションの中で、グールドとスコットのテイクを数える役割の奪い合いがあったことも、それをうかがわせる。グールドのような演奏家がレコーディング・スタジオに入ってきたことは、エンジニアやプロデューサーを身構えさせるものだったに違いない。
テープ編集を重視するグールドの録音哲学が広く知られるようになったのは1960年代になってからで、彼がコンサート活動を休止したことから、センセーショナルに報じられた。1962年にはグールドは公演旅行に出ることはしないと宣言し、1964年にはコンサート活動から完全に引退した。同時に、レコーディングの可能性や意義について、積極的に語るようになった。
https://www.cbc.ca/player/play/1784236919
カナダの音楽学者、ジェフリー・ペイザントが1981年に著した『グレン・グールド なぜコンサートを開かないか』は、グールドの研究書として最も有名な一冊だが(2007年には『グレン・グールド、音楽、精神』のタイトルで改訂版が邦訳されている)、この中でペイザントは面白い指摘をしている。グールドは6歳のときに、初めてピアニストの演奏会に足を運んだ。それはポーランド出身のピアニスト、ヨゼフ・ホフマンのコンサートだったが、そのホフマンこそはトーマス・エジソンのために録音を行った最初のクラシック・ピアニストであるとペイザントは書いている。
ジェフリー・ペイザント 宮澤淳一/訳
(音楽の友社/2007年)
グールドに関する初の学術的研究書『グレン・グールド なぜコンサートを開かないか』(1981年)の新訳版。グールド研究者による新訳では、旧訳版で割愛された部分を増補するとともに、初版刊行後に著者が記したテキストなどが加えられた
1876年生まれのヨゼフ・ホフマンは10歳にして、早熟なピアノの天才としてヨーロッパ各地をツアー。1887年の終わりには、11歳にしてアメリカに赴き、翌年にかけて公演旅行を行った。ホフマンはそこでシリンダー式のPhonographを完成させたばかりのエジソンと知り合い、1888年にエジソンのためにピアノ演奏を録音したとされている。音源は現存しないものの、このエピソードが事実ならば、ホフマンが録音活動を行った最初のクラシック演奏家だった可能性は高い。

ホフマンとエジソンはその後も文通を続け、エジソンはベルリンに住むホフマンにPhonographを1台贈った。ホフマンはその後、発明家としても活動し、さまざまな特許を取得して、財を成したという。そんなホフマンに啓示を受けたグールドが、レコーディング・アーティストとしての活動に専念することを選んだ最初のクラシック演奏家となったことは、確かに偶然とは思いがたい。
数々の名匠を生み出したコロムビアのエディティング・ルーム
グールドがテープ編集を駆使した録音術について語り、それが賛否両論を巻き起こすようになったのは1964年のコンサート活動の休止と前後するが、グールドの録音作品にテープ編集が使われるようになったのは、もっと前からだと思われる。というよりも、グールドに限らず、コロムビア・マスターワークスで制作されるクラシック音楽作品においては、1950年代からプロデューサーの権限によるテープ編集が行われていたようだ。演奏や録音の小さなミスをテープ編集で解消する技術は、ジョージ・アヴァキアンらによって、かなり確立されていた。

そうしたテープ編集はレコーディング・スタジオではなく、専用の編集室で専任のスタッフによって行われた。コロムビア・レコードのこのエディティング・ルームは、音楽史に名を残す、多くの人材を輩出したことでも知られる。マイルス・デイヴィスのプロデューサーとして名高いテオ・マセロも、1956年にジョージ・アヴァキアンがテープ・エディターとして雇い入れたことから、コロムビア・レコードのスタッフになっている。
1964年からサイモン&ガーファンクルのエンジニアを務め、ポール・サイモンのアルバムにも多く貢献したエンジニアのロイ・ハリーもこのエディティング・ルームで働いていた。ハリーの場合は1950年代終わりにCBSに入社。CBSテレビの仕事をしていたが、1960年代始めのリストラでコロムビア・レコードに回され、テープ編集の仕事に就いた。ミュージシャンとは会うことがなく、テオ・マセロなどのプロデューサーが持ち込むテープの編集だけをする日々だった。

www.historyofrecording.com/royhalee.html
ところが、サイモン&ガーファンクルという新人のデモ録音を行う日に、エンジニアが足らず、ハリーがレコーディング・スタジオに駆り出された。サイモン&ガーファンクルは彼の仕事ぶりを気に入り、そのまま、ハリーは彼らのデビュー・アルバム『水曜の朝、午前3時』(1964年)の録音を任されることになった。ポール・サイモンの『グレイスランド』(1986年)や『ストレンジャー・トゥ・ストレンジャー』(2016年)も手掛けた名匠は、そんな偶然から、30歳を過ぎてレコーディング・エンジニアになったのだ。

Simon & Garfunkel
(Columbia/1964年)
1957年に別名義でデビューしていた2人は、本作で再デビュー。収録曲「サウンド・オブ・サイレンス」がカレッジ・ラジオで徐々に人気が出て、翌年オーバー・ダビングを行ったシングルをリリースし、ヒットに至る
グールドの理想のピアノが生み出す“しゃっくり”をテープ編集で取り除く試み
コロムビア・マスターワークスのプロデューサーとして、グールドの録音を多く手掛けたアンドリュー・カズディンも、入社当初はテープ編集の仕事に就いていた。彼の入社は1964年だというから、ちょうどロイ・ハリーがエディティング・ルームを飛び出していったころだろう。
カズディンがグールドの死後の1989年に著した『グレン・グールド アットワーク』は、グールドと多くの仕事を共にした人間による内幕本とも言える一冊だ。グールドの伝説として語られていることの多くは、グールド自身が作り上げた虚像であるという辛らつなメッセージも放つが、レコーディング・スタジオで実際に起こったことを詳細に記録した内容であり、興味深いエピソードが連続する。
アンドリュー・カズディン 石井晋/訳
(音楽の友社/1993年)
15年にわたってグールド作品のプロデューサーを務めてきたカズディンによる著書。グールド自身の言葉ではなく、カズディンの視点から見たグールドが描かれている点が貴重な資料とされる
『グレン・グールド アットワーク』で最初に話題になるのは、グールドのピアノが引き起こす“しゃっくり”(hiccup)だ。カズディンがコロムビアに入社した1964年にグールドはアルバム『インヴェンションとシンフォニア』を録音した。『ゴールドベルク変奏曲』の8年後に、練習曲としてよく知られるバッハの曲を弾いたこのアルバムは、彼のコンサート活動休止後の最初のリリースでもあった。そして、その録音において顕在化したのが、ピアノの“しゃっくり”問題だった。

Glenn Gould
(Columbia Masterworks/1964年)
2声のインヴェンションと3声のシンフォニア、それぞれ全15曲を収録。現行CDは『イギリス組曲』もコンパイルし、ソニー・クラシカルよりリリース
『インヴェンションとシンフォニア』に使われたのは、STEINWAY CD318というピアノだった。グールドは1960年にトロントのイートン・オーディトリアムでそれを発見した。グールドは理想のピアノを追い求めて、数年間、世界各地に足を運んでいたが、それは地元のホールで14年間酷使され、役目を終えようとしていたピアノだった。
そのCD318に特別なものを感じたグールドは、カナダのサスカチュワン州出身の調律師、ヴェルヌ・エドキストにその再生を依頼した。エドキストがグールドの厳しい要求に応えて調整したCD318は、1963年にはニューヨークのコロムビア30丁目スタジオに運び込まれた。そして、同年9月18日に『インヴェンションとシンフォニア』が始まる。しかし、グールドはCD318のアクションに満足しなかったため、レコーディングは中断。エドキストとともにピアノの再調整を重ねた後、本セッションは1964年3月18〜19日に行われた。
グールドの好みに合わせて、機械的反応性を高めたCD318が抱えたこの“しゃっくり”について、カズディンはこう説明している。ハンマーを極限まで弦に近付けてセットアップしたCD318は、時にハンマーの動きを制御しきれなくなり、弦を2度打ちする。それがこだまのような音を付け加えてしまう。彼がコロムビアのエディティング・ルームに入ったとき、技術者の間ではその“しゃっくり”をテープ編集でどこまで取り去れるかが話題だったという。
『インヴェンションとシンフォニア』のプロデューサーはポール・マイヤーズだった。グールドは『ゴールドベルク変奏曲』以後、11枚のアルバムをハワード・H・スコットとともに制作したが、その後、プロデューサーはジョゼフ・シャンニに代わり、さらにポール・マイヤーズに代わった。『インヴェンションとシンフォニア』のレコーディングは2日間で終わったが、マイヤーズとグールドはそこから長い編集作業に入った。“しゃっくり”を取り去れるか、そして、取り去るべきなのか、という議論を2人は繰り返したようだ。

Paul Myers | ディスコグラフィー | Discogs
“しゃっくり”(hiccup)という言葉を使い出したのはグールドで、それを引き起こすようなピアノの調整を望んだのもグールド自身だった。故に、その“しゃっくり”はグールドにとっては友人のようなものだったとカズディンは論じている。
それでも、ポール・マイヤーズとテープ編集技師たちは最大限、それを取り除こうとした。ピアノが発する偶発的なゴースト・ノートを取り除く作業は現代のDAW上でも、難しいものになるだろう。だが、1960年代に彼らはテープ編集でそれを行っていた。オリジナル・テープは切り刻めないから、何本ものコピーを作り、そのワンノートだけを同じテイクの別の個所から、あるいは別テイクから切り出して張り付けるような作業が行われたのだと思われる。
だが、『インヴェンションとシンフォニア』においては、完全には“しゃっくり”を取り去れない部分も残った。切り張りによって、思いがけないノートの音量差が付いてしまった部分もあった。このため、STEINWAYにも配慮して、アルバムのライナーノーツでグールド自身が釈明を加えることになった。その大意は以下のようなものだった。
バッハを演奏するのに不可欠なノン・レガートの響きを得るために、CD318は大手術を受けた。だが、小さな後遺症が残った。中音域に“しゃっくり”のような音が聴こえる。とはいえ、セッションの中で私はこの楽器特有のそれにかなりなじみ、魅力的な特異体質と感じるようにもなった。将来的にはこの響きを保ちながら、“しゃっくり”を減らしたいが、今はまだ調整中だ。


高橋健太郎
音楽評論家として1970年代から健筆を奮う。著書に『ポップ・ミュージックのゆくえ』、小説『ヘッドフォン・ガール』(アルテスパブリッシング)、『スタジオの音が聴こえる』(DU BOOKS)。インディーズ・レーベルMEMORY LAB主宰として、プロデュース/エンジニアリングなども手掛けている。音楽配信サイトOTOTOY創設メンバー。
Twitterアカウントは@kentarotakahash
Photo:Hiroki Obara